「デザイン経営は見た目を整えることではない」
——経営にデザインを持ち込む最大の意味は、問いを立てる力にあります。
Problem|「デザイン経営=見た目」の誤解
「デザイン経営」と聞くと、多くの人がロゴ刷新や製品の美しいUIを想像します。
しかし、それは本質の一部にすぎません。
経済産業省の「デザイン経営宣言」でも指摘されているように、デザインは経営戦略やイノベーションの源泉であり、単なる装飾ではありません。
見た目に終始した“表層的なデザイン導入”は、一時的な注目を集めてもブランド価値の持続的成長にはつながらないのです。
Empathy|「問い」がなければ、形は迷走する
- どの顧客の課題を解決するのか?
- その事業は未来の社会に必要とされるのか?
- ブランドとして、どんな関係性を築きたいのか?
これらの問いを持たずに「形」だけ整えようとすると、企業は迷走します。
一方で、良質な問いは経営の軸を強固にし、社員の意思決定を支える羅針盤になります。
実際、IDEO や Apple といった企業は「顧客の生活体験にどう寄与するか?」という問いを徹底的に掘り下げることで、革新的な事業を生み出し続けています。
Solution|「問いのデザイン」が経営を変える
デザイン経営の本質は「問いをデザインすること」。
形やアウトプットは、その問いへの応答として生まれる結果にすぎません。
ポイントは3つです。
- 未来起点で問いを立てる
現状の改善ではなく、3〜5年後の顧客・社会を見据える。 - 多様な視点を持ち込む
デザイナーだけでなく、経営者・現場社員・顧客の声を交え問いを洗練させる。 - 問いを検証可能にする
定性的な問いを実験やプロトタイピングで検証し、学習サイクルを回す。
これにより、経営そのものが「探索」と「学習」のプロセスへと変わります。
Action Steps|今日からできる実践
- 経営会議で「問い」を議題にする
売上やコストの数値だけでなく、「次の成長を導く問いは何か?」を定例化する。 - 社内プロジェクトで仮説検証を導入
新規事業や改善提案を「問い→仮説→実験」の流れで運用する。 - 問いを見える化する
ホワイトボードやデジタルツールに「今の問い」を掲示し、組織全体で思考を共有する。
Future Vision|問いが未来を形づくる
問いをデザインする文化を持つ企業は、形に惑わされず、自ら未来を切り拓きます。
社員一人ひとりが「どんな問いを立てられるか」で組織の成長速度が変わるのです。
デザイン経営は、特別な企業だけのものではありません。
小さな問いを持ち続けることこそ、平凡な組織を非凡に変える第一歩となります。
関連記事リンク
CTA|問いかけ
あなたのチームや組織で、今もっとも重要だと思う「問い」は何ですか?
ぜひコメント欄やSNSでシェアしてください。
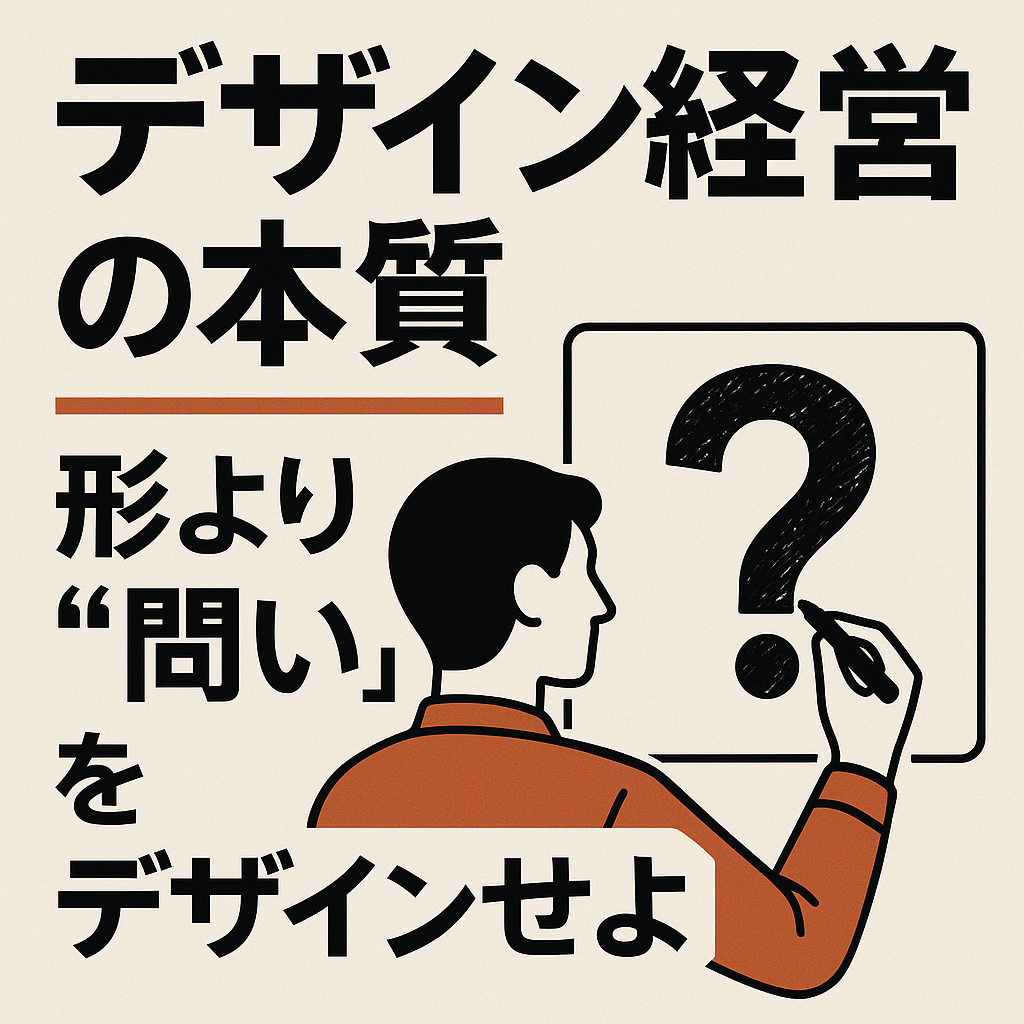
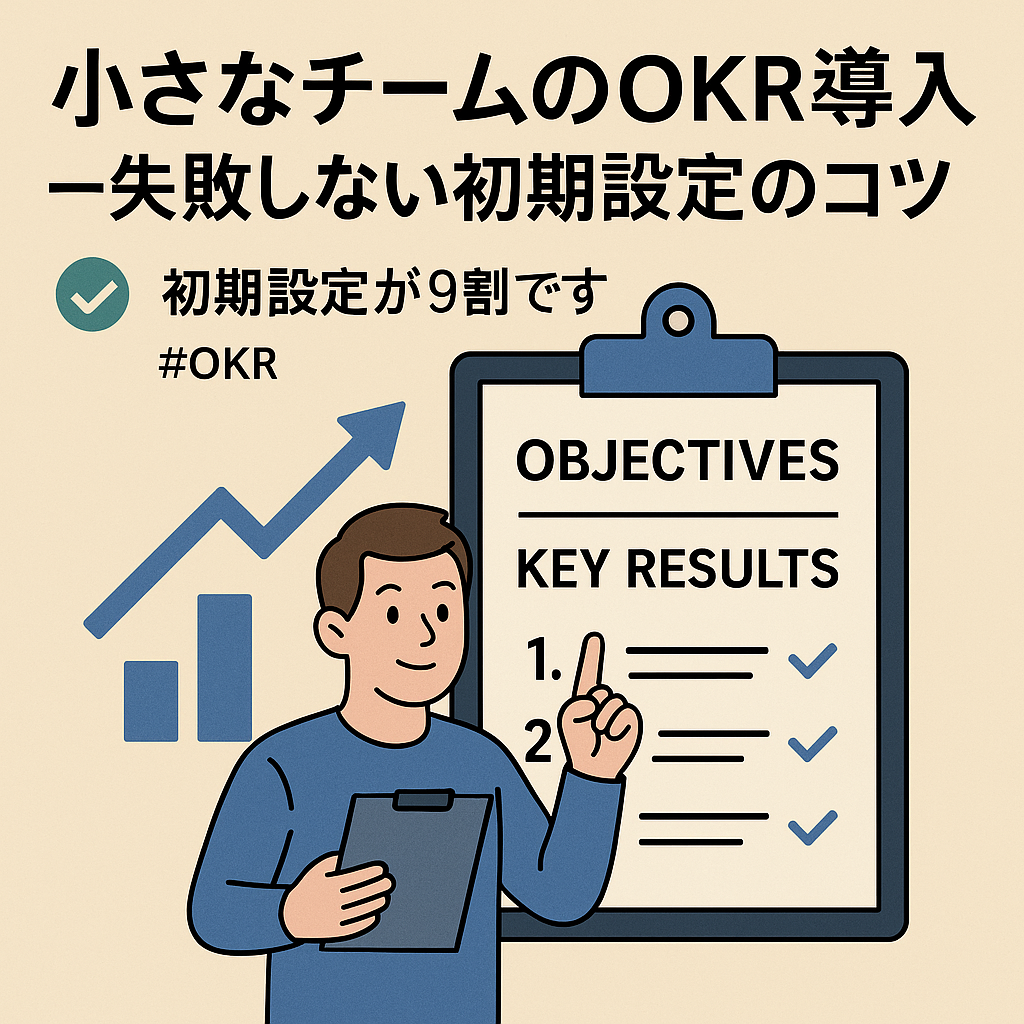
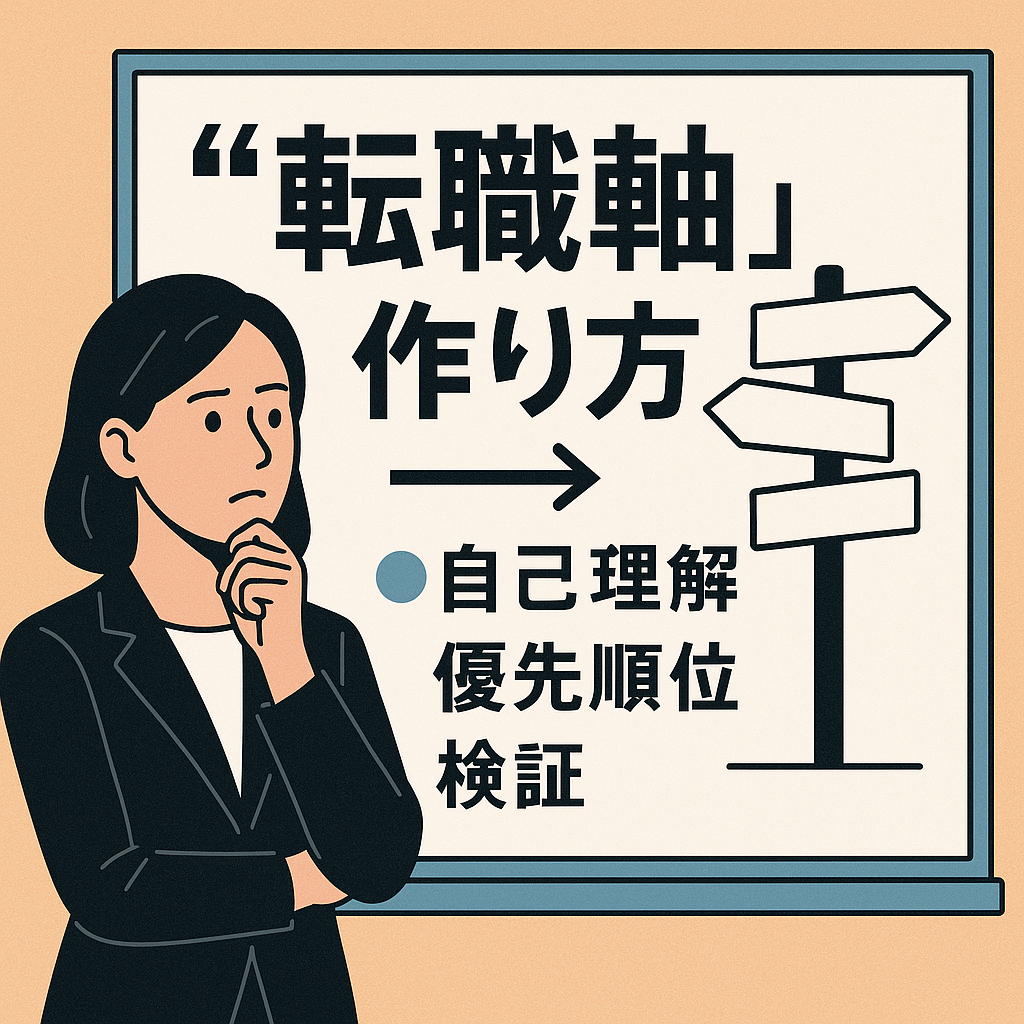
コメント